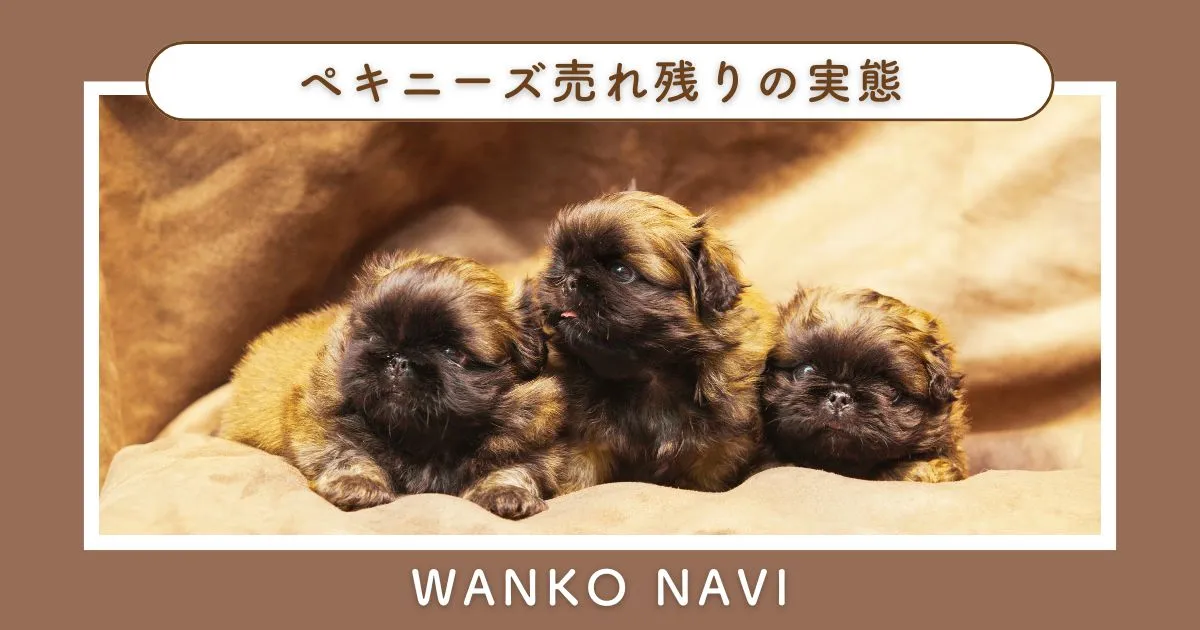「ペキニーズってかわいいけど、売れ残りって本当に多いの?」
そんな疑問や不安を抱えて検索された方は少なくありません。
見た目に惹かれて調べ始めたものの、売れ残りという言葉に戸惑った方もいるでしょう。
ペキニーズは独特な性格や飼育上の特徴から、思わぬ理由で新しい家族と出会えずに残ってしまうことがあります。
この記事では、「ペキニーズ 売れ残り」の実態を明らかにしながら、後悔しないために迎える前に絶対に知っておきたい知識を丁寧に解説していきます。
性格・お手入れ・価格・販売事情・保護の選択肢まで、実際に飼う前に知っておくべき情報を網羅しているので、この記事を読めば、ペキニーズと幸せな未来を築くための準備が整うはずです。
- ペキニーズが売れ残りになる主な理由
- ペットショップでの売れ残りの実態
- 売れ残ったペキニーズの行き先と現状
- 迎える前に知っておくべき飼育の注意点
ペキニーズの売れ残りはなぜ起きる?

ペキニーズは見た目の可愛らしさや高貴な雰囲気から、人気がある犬種の一つです。しかし、ペットショップなどで売れ残ってしまうケースも少なくありません。なぜペキニーズが売れ残ってしまうのか、その背景にはいくつかの理由があります。
この記事では、性格の特徴や飼いやすさ、お手入れの難しさ、そして価格の面から「売れ残り」の原因を詳しく解説していきます。
- ペキニーズってどんな性格?実はマイペースな子が多い
- お手入れがちょっと大変?被毛のケアと健康面の注意点
- お値段が高め?価格で迷う人が多い理由
- 飼い主に求められる「相性」と「覚悟」
- ペットショップと売れ残り問題のつながり
- ペキニーズの激安販売は大丈夫?注意しておきたいこと
- ペキニーズ個人販売のメリットとリスク
ペキニーズってどんな性格?実はマイペースな子が多い
ペキニーズは「まるで猫のような性格」と言われるほど、自分のペースを大切にする犬種です。一般的な「従順な犬」というイメージとは異なり、独立心が強く、抱っこや過度なスキンシップを好まない子もいます。このような性格は、初めて犬を飼う人にとっては少し扱いづらいと感じられるかもしれません。
また、プライドが高く頑固な一面もあるため、しつけに時間がかかることもあります。飼い主の言うことを理解していながらも、「今はやりたくない」といったような態度を見せることがあるのも特徴です。こうした性格が、しつけや接し方に不安を抱える人にはハードルに感じられてしまうのです。
さらに、ペキニーズは他の犬や見知らぬ人に対して距離をとる傾向があります。警戒心が強く、自分のテリトリーを大事にするため、多頭飼いや人の出入りが多い環境にはあまり向いていないケースもあります。反対に、静かな暮らしを求める人や単身者にとっては、程よい距離感を保てるパートナーとして向いているでしょう。
その一方で、信頼関係を築いた相手にはとても忠実で愛情深く接するため、じっくりと向き合える飼い主さんには最良のパートナーになります。愛情の表現方法が控えめで、常に甘えてくるタイプではありませんが、寄り添うようにそばにいる時間が長くなるのもペキニーズの魅力の一つです。
このように、ペキニーズの性格は独特で、理解が必要です。その点が「売れ残り」という現象の一因になっていると考えられます。見た目のかわいらしさだけではわからない性格面を知った上で、しっかり向き合える飼い主が必要とされる犬種です。
お手入れがちょっと大変?被毛のケアと健康面の注意点
ペキニーズの魅力のひとつは、ライオンのたてがみのようなふさふさの被毛です。しかしその美しさを保つには、こまめなお手入れが欠かせません。特にダブルコートという毛質は、毛が絡まりやすく、毛玉ができやすい傾向があります。
毎日のブラッシングは理想的で、少なくとも週に2〜3回はしっかりと手入れをする必要があります。放っておくと毛玉ができ、皮膚の通気性が悪くなり、皮膚病やかゆみの原因になってしまうことも。加えて、顔周りのシワの部分も汚れが溜まりやすいため、毎日きれいに拭き取る習慣も大切です。
また、ペキニーズは短頭種のため、呼吸器系のトラブルが起きやすい犬種でもあります。暑さに非常に弱く、夏場はエアコンを使って室内温度を管理するなどの配慮が必須です。熱中症のリスクも高いため、真夏の散歩は早朝や夜間に限定することが望ましいでしょう。
さらに、足が短く体重が骨にかかりやすいため、膝や背骨に負担がかかりやすいことにも注意が必要です。フローリングで滑ってしまわないよう、床にはマットやカーペットを敷いておくと安心です。
このように、ペキニーズの健康を守るには「日々のお手入れと環境づくり」がとても重要です。見た目のかわいらしさとは裏腹に、手間のかかる犬種であることを知っておく必要があります。
お値段が高め?価格で迷う人が多い理由

ペキニーズは、他の小型犬と比べて価格が高めに設定されていることが多い犬種です。ペットショップやブリーダーによって違いはありますが、相場は20万円〜40万円ほどになるケースが一般的です。見た目が可愛いわりに、手頃な価格ではないことが、購入をためらう理由のひとつになっています。
この価格の背景にはいくつかの理由があります。まず、ペキニーズは一度の出産で生まれる頭数が少ない傾向にあり、供給量が限られていることが影響しています。さらに、体が小さく、出産にもリスクが伴うため、ブリーディングの難易度が高いことも価格に反映されています。
また、ペキニーズはその独特な見た目や血統によって、ショードッグ向けの個体にはさらに高い値段が付くことも。親犬のチャンピオン歴などが影響するため、血統書付きの個体では30万円を超えることも珍しくありません。
価格が高いため、他の犬種に比べて慎重に検討されることが多くなります。特に初めて犬を飼う人にとっては、「せっかく高いお金を出しても飼いきれるだろうか?」という不安が生まれやすく、それが売れ残りの要因のひとつになっている可能性もあります。
もちろん、価格が高いからといって価値が低いわけではありません。飼い主との相性や生活スタイルに合っているかどうかが、選ぶうえでの本当の判断基準になるでしょう。
飼い主に求められる「相性」と「覚悟」
ペキニーズはそのかわいらしい見た目とは裏腹に、個性的で自立心の強い性格を持つ犬種です。そのため、ただ「可愛いから」という理由だけで迎えると、後悔してしまう可能性もあります。ペキニーズと長く幸せに暮らすためには、飼い主との相性と覚悟がとても重要です。
まず、相性の面では、ペキニーズはべったり甘えるタイプではなく、自分の時間を大切にしたいタイプ。猫のようなマイペースさを持っているため、四六時中かまってほしい人や、犬と常に触れ合っていたい人には少し物足りなく感じるかもしれません。一方で、お互いの距離感を大切にできるタイプの人には、ちょうどよい関係性を築けるパートナーになります。
また、頑固な性格をしているため、しつけには根気強さと一貫性が求められます。すぐに覚える犬種ではないので、感情的にならず、地道にトレーニングを重ねる必要があります。「叱る」より「褒めて伸ばす」しつけ方法が向いているのも、ペキニーズの特徴です。
覚悟という点では、毎日のお手入れや健康管理に手を抜けない犬種であることを理解することが大切です。顔や毛の手入れ、暑さ対策、関節への配慮など、細かなケアを必要とします。さらに、短頭種ゆえの医療リスクや、将来の介護の可能性も含めて、長期的な責任を持てるかどうかが問われます。
ペキニーズは「育てやすい犬」ではなく、「理解して向き合える人にだけ本当の魅力を見せてくれる犬」と言えます。一緒に暮らす覚悟と愛情があれば、かけがえのない家族になることは間違いありません。
ペットショップと売れ残り問題のつながり
ペットショップで販売されている子犬たちの中には、一定の期間を過ぎても買い手が見つからず、売れ残ってしまうケースがあります。ペキニーズもその対象となることがあり、「かわいいのに、なぜ売れ残るの?」と感じる人も少なくありません。その背景には、ペットショップの販売スタイルや流通の仕組みが大きく関係しています。
ペットショップでは、生後2〜3ヶ月の子犬が「一番売れやすい時期」とされます。この時期を過ぎると、見た目の印象やサイズ感が変わり、購入希望者が減っていくのです。また、スペースやコストの都合で、売れない子犬は新しい犬に入れ替える必要が出てくるため、結果的に売れ残りが発生します。
売れ残ったペキニーズの行き先としては、価格を大幅に下げて販売を継続する、他店舗に移動させる、もしくはブリーダーに戻されるケースがあります。しかし、なかには引き取り業者に渡されてしまうこともあり、その先の運命は決して明るいとは限りません。
このように、ペットショップでの販売は「可愛い子犬をすぐに飼える」という利便性がある一方で、売れ残ることで命の価値が軽視されてしまう現実も抱えています。売れ残り問題を根本的に解決するには、衝動買いや見た目だけでの選択を控え、命を迎えることへの責任をしっかりと考える意識の広がりが必要です。
ペキニーズの激安販売は大丈夫?注意しておきたいこと

インターネットや一部のペットショップでは、「激安」と表記されたペキニーズが販売されていることがあります。一見するとお得に感じるかもしれませんが、安さの裏には見落とせないリスクが潜んでいることもあります。価格だけで判断する前に、注意すべきポイントを知っておきましょう。
まず、激安の背景には「売れ残り」や「何らかの問題がある個体」などの理由が隠れている場合があります。例えば、健康上の不安がある、社会性を育てる時期をペットショップで過ごしてしまった、あるいは血統的な欠点があることなどが考えられます。これらはすぐに見た目で判断できるものではなく、迎えてから問題が表面化することもあります。
また、ブリーダーや販売元が十分な飼育環境を提供していない可能性も見逃せません。悪質な業者の場合、十分なワクチン接種がされていない、感染症の予防が不十分、さらには虚偽の情報を伝えて販売するケースも報告されています。
もちろん、すべての激安販売が悪いというわけではありません。事情により価格を下げてでも早く飼い主を見つけたいと考えている良心的なブリーダーもいます。重要なのは、「安いから買う」のではなく、「きちんと信頼できる相手から迎えるかどうか」を見極めることです。
購入を検討する際は、販売元と直接会って犬の状態を確認したり、過去の飼育記録を見せてもらうことが大切です。安さだけに目を奪われず、一生を共にする存在としての責任を忘れずに選びましょう。
ペキニーズ個人販売のメリットとリスク
最近では、ブリーダーからの直接販売や、個人同士のやりとりでペキニーズを迎えるケースも増えてきました。ペットショップを介さずに迎える「個人販売」には、いくつかのメリットがありますが、同時に注意すべきリスクも存在します。冷静に両面を理解したうえで選択することが大切です。
メリットとしてまず挙げられるのが、中間マージンが省かれるため価格が比較的抑えられることです。ペットショップよりも安価にペキニーズを迎えることができる点は、予算に限りのある家庭にとっては大きな魅力です。また、個人のブリーダーから直接迎える場合、親犬の性格や健康状態、飼育環境などを詳しく確認できるという利点もあります。
一方で、リスクもあります。個人販売の場合、健康保証やアフターサポートがないことがほとんどです。迎えた直後に病気が発覚しても、治療費やサポートが受けられない可能性があるため、事前にしっかり確認しておく必要があります。
また、法律的なトラブルや詐欺に巻き込まれるリスクもゼロではありません。特にインターネットを通じてやりとりする場合は、顔の見えない取引になるため、信頼性を見極めるのが難しくなります。やりとりの履歴を残す、契約書を交わすなど、慎重な対応が求められます。
個人販売は、信頼できる相手と出会えれば、安心して新しい家族を迎えることができる方法でもあります。そのためには、焦らず時間をかけて情報を集め、自分に合った相手と出会う準備をしておくことが大切です。
ペキニーズの売れ残りを救う選択肢とヒント

ペキニーズが売れ残る背景にはさまざまな理由がありますが、大切なのはその子たちに新たな居場所を与える選択肢があるということです。近年では、保護犬の譲渡や里親制度を通じて、新しい家族を探しているペキニーズも少なくありません。
この記事では、売れ残りや保護されたペキニーズを救うために、どのような手段があるのかを紹介していきます。
- ペキニーズ里親無料で探せるって本当?
- ペキニーズ子犬譲ります情報はどこで見つける?
- ペキニーズの保護犬を迎えるという選択肢
- 飼ってから後悔?よくあるギャップとは
- ペキニーズの性格を知っておけば後悔しない
- 売れ残ったペキニーズはどこへ行くの?
- 保護団体や引取り屋の実態を知っておこう
- 売れ残りを減らすには?私たちにできること
- ペキニーズの売れ残りに関するよくある質問
- ペキニーズが売れ残りになる理由を総括
ペキニーズ里親無料で探せるって本当?
結論からいえば、「ペキニーズの里親を無料で探すことは可能」です。ただし、まったくお金がかからないという意味ではなく、「生体の譲渡にお金が発生しない」という点に注目すべきでしょう。多くの保護団体や譲渡会では、譲渡費用はかかりませんが、医療費の一部や譲渡手続きに伴う費用が必要になるケースがあります。
ペキニーズは人気のある犬種であり、年齢や性格にこだわらなければ、保護犬として出会える可能性は十分にあります。全国には「ペキニーズレスキュー」や「犬の里親募集サイト」など、特定の犬種に特化した団体や、広範なマッチングを行うウェブサイトが存在します。インターネットで「ペキニーズ 里親 無料」と検索することで、候補を見つけることができるでしょう。
ただし、里親制度を利用するには、譲渡条件や審査をクリアする必要があることを理解しておくことが大切です。例えば、終生飼育の意思があるかどうか、家族全員の同意があるか、適切な飼育環境が整っているかなどが確認されます。条件が厳しいと感じるかもしれませんが、これは犬の幸せを第一に考えるために必要なステップです。
また、無料で迎えるからといって経済的な負担がゼロになるわけではありません。迎え入れた後には、ワクチン接種、定期的な健康診断、食費、トリミング代などがかかります。「無料だから」と安易に考えず、一生のパートナーとしての責任を持つことが何より大切です。
結果として、ペキニーズの里親を無料で探すことは現実的な選択肢ですが、それに伴う責任や準備も忘れてはいけません。無償であっても、命を預かるという意識を持って行動することが、幸せな出会いにつながる第一歩になるでしょう。
ペキニーズ子犬譲ります情報はどこで見つける?
ペキニーズの子犬を探していると、「譲ります」という言葉を見かけることがあります。これにはペットショップとは異なり、個人や団体が里親を募集している場合や、ブリーダーが直接譲渡しているケースが含まれます。ペットショップよりもコストが抑えられることがあるため、関心を持つ人も少なくありません。
具体的に「譲ります」情報を見つけるには、インターネット上の里親募集サイトや掲示板、SNSをチェックするのが基本です。「OMUSUBI」「ペットのおうち」「ジモティー」などのサイトでは、地域や犬種を絞って検索できます。こうしたサイトでは、登録者が子犬の写真や性格、譲渡条件を詳しく記載していることが多く、比較検討しやすいのが特徴です。
一方、信頼できるブリーダーからの譲渡を希望する場合は、「ペキニーズ専門ブリーダー」や「優良ブリーダー直販サイト」などのキーワードで検索するのが良いでしょう。見学が可能か、親犬の様子が見られるかなども、チェックすべきポイントです。
ただし、「譲ります」と書かれていても、譲渡の際にワクチン代や医療費を請求されることは珍しくありません。実質的に数万円程度の費用がかかることがあるため、事前にしっかり確認しましょう。
また、あまりにも安すぎる価格や不自然な条件には注意が必要です。動物を「モノ」として扱うような投稿や、詳細な情報を開示しないケースはトラブルの原因になりかねません。疑問点がある場合は、やり取りの段階で納得できるまで確認することが大切です。
情報収集には少し手間がかかるかもしれませんが、それだけに信頼できる出会いにたどり着けた時の喜びも大きいはずです。
ペキニーズの保護犬を迎えるという選択肢

ペキニーズを家族に迎えたいと考える中で、「保護犬」という選択肢に注目する方が増えています。保護犬とは、何らかの理由で飼い主を失った犬や、売れ残ってしまった子犬たちを指し、新たな飼い主を探している犬のことです。
特にペキニーズはペットショップで人気がある一方、成長とともに売れ残ることもあり、保護団体に引き取られて里親を募集されるケースもあります。また、飼育放棄や高齢者の事情によって手放された個体も見受けられます。
保護犬を迎えるメリットのひとつは、新しい命にチャンスを与えることができるという社会的意義です。売買ではなく、あくまで保護と譲渡を目的としているため、ビジネス色が薄く、動物愛護の観点から支持されている方法でもあります。
さらに、多くの保護団体では事前に健康診断や避妊去勢手術を済ませてくれている場合が多く、初期費用がわかりやすいのもポイントです。もちろん譲渡にかかる費用(医療費負担など)はありますが、生体購入に比べれば負担は軽く済むことが多いです。
ただし、注意したいのは「保護犬だからしつけが不要」というわけではない点です。過去の経験から人間に対して警戒心を持っている子や、トラウマを抱えている子もいます。だからこそ、迎える側の理解と根気が必要です。
また、団体によっては事前の面談や飼育環境のチェックが行われ、譲渡条件が設定されています。条件が厳しいと感じるかもしれませんが、これは犬の幸せを第一に考えているからです。
このように、保護犬のペキニーズを迎えることは、命をつなぐだけでなく、家族として深い絆を育むきっかけにもなります。
飼ってから後悔?よくあるギャップとは
ペキニーズは見た目の可愛らしさと高貴な雰囲気から、「飼いやすそう」「おとなしい子かも」といった印象を持たれがちです。しかし、実際に飼い始めてから「思っていたのと違った」と感じる人も一定数います。このギャップが、飼い主の後悔につながることもあるのです。
よくあるのは、「性格の予想外さ」です。ペキニーズは基本的にマイペースで頑固な一面があり、しつけに時間がかかることがあります。飼い主に忠実ではあるものの、すぐに言うことを聞いてくれるタイプではありません。指示を無視されたり、トイレの失敗が続いたりすると、しつけに苦労する可能性があります。
また、被毛の手入れが予想以上に大変だという声も少なくありません。長毛のダブルコートは毎日のブラッシングが必要で、毛玉ができやすいため丁寧なケアが欠かせません。トリミングやシャンプーも定期的に行う必要があり、忙しい人には負担に感じることがあります。
さらに、健康面でも注意が必要です。ペキニーズは短頭種であるため、暑さに弱く、呼吸器系のトラブルも起こりやすい犬種です。エアコンがないと夏場は命の危険にさらされることもあり、室温管理は必須です。
このような点を知らずに飼い始めると、「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうことがあります。大切なのは事前にしっかりと情報を集め、自分の生活スタイルと照らし合わせて考えることです。見た目だけで決めず、性格や必要なケア、費用、生活環境などを総合的に見たうえで決断すれば、後悔のない犬との生活が送れるはずです。
ペキニーズの性格を知っておけば後悔しない
ペキニーズは、見た目の愛らしさと裏腹に、実は「猫のような性格」とも言われるマイペースな犬種です。この性格をよく知らずに迎えると、飼い主との相性にズレが生じ、後悔するケースもあります。だからこそ、性格をしっかり理解することがとても重要です。
ペキニーズは自立心が強く、抱っこや過度なスキンシップを好まない子も多いです。甘えるときもあれば、突然そっけなくなることもあり、まさに“ツンデレ”な気質が特徴です。また、自分のペースを大切にするため、急な環境の変化やしつけに対しても敏感に反応します。
一方で、飼い主に対しては非常に誠実で、強い信頼関係を築けるタイプでもあります。時間をかけて関係を深めていくことで、落ち着いた信頼の絆が生まれます。
問題となりやすいのが、しつけの難しさです。プライドが高いため、命令口調や叱責には反発しやすく、根気よく、褒めて伸ばすスタイルが基本になります。また、他の犬や見知らぬ人に対しては距離を置く傾向があり、無理に近づけるとストレスになることも。
このような性格を事前に理解し、「犬だから常に懐いてくる」というイメージを持ちすぎないことが大切です。ペキニーズは一緒に暮らすパートナーとして、静かで落ち着いた関係を好むタイプ。無理に関係を深めようとするよりも、適度な距離感を保ちながら、じっくり信頼を築くことができる人に向いています。
売れ残ったペキニーズはどこへ行くの?

ペットショップで販売されていたペキニーズが売れ残った場合、その行き先はさまざまです。特に日本では「生体販売」が一般的であるため、売れなかった場合の対応は店によって異なりますが、必ずしも明るい未来が待っているとは限りません。
一般的に、生後3か月を過ぎると子犬の販売価格は下がり始めます。それでも売れない場合、多くの店舗ではブリーダーへの返却や「引取り業者」への譲渡が行われることがあります。一部では、保護団体と連携して里親探しを行っている良心的な店もありますが、それはまだ少数派です。
返却されたペキニーズは、繁殖犬として利用されたり、劣悪な環境で過ごすことになったりすることもあります。さらに、最悪の場合は処分対象になってしまうケースもあり、これが大きな社会問題となっています。
また、「引取り屋」と呼ばれる業者は、ペットショップやブリーダーから不要となった犬を一括して引き取りますが、その管理体制は不透明で、十分なケアが行われていない例も多く報告されています。中には衛生面に問題があったり、必要な医療を受けられなかったりするケースもあるのです。
このように、売れ残ったペキニーズの行き先は一様ではありませんが、適切な飼い主に出会えるチャンスは非常に限られているのが現実です。だからこそ、命の扱いに対する私たちの意識が問われているとも言えます。
保護団体や引取り屋の実態を知っておこう
ペット業界の裏側には、保護団体や引取り屋と呼ばれる存在があります。一見どちらも「売れ残りや飼育放棄された動物を受け入れる存在」として同じように見えますが、実態は大きく異なります。正しく理解することが、犬を迎える私たちの責任にもつながります。
保護団体は、保健所からの引き取りや飼い主からの相談を受けて、犬の新しい里親を探す非営利の組織です。犬の健康管理や性格の評価、適切な譲渡まで丁寧な対応をしている団体が多く、譲渡前には面談や飼育環境の確認も行われます。また、医療処置が済んでいる場合が多く、安心して迎え入れることができます。
一方、引取り屋は営利目的で動いているケースが多く、ペットショップやブリーダーから不要になった犬を有料で引き取る代わりに、その後の管理はずさんなことが少なくありません。報道でも問題視されており、食事や医療が十分に行き届かず、過酷な環境下で放置されることもあります。
さらに、表面上は保護団体を装って活動している悪質な業者も存在します。犬の扱いや施設の様子を公開しない団体には警戒が必要です。見学や譲渡条件を曖昧にする団体には注意を払い、口コミや第三者の評価も確認しましょう。
私たちが犬を迎える立場としてできるのは、こうした実態を正しく知り、信頼できる団体から譲渡を受けることです。犬の命に関わる選択だからこそ、情報に基づいた行動が求められます。
売れ残りを減らすには?私たちにできること
ペキニーズに限らず、「売れ残り」という言葉が生まれてしまう背景には、動物を商品として扱うペット流通の仕組みがあります。需要と供給のバランスが崩れると、生まれてきた命が飼い主を得られないまま行き場を失うことになるのです。これを防ぐためには、私たち一人ひとりの意識と行動が欠かせません。
まずできることは、「命を迎える選択肢を慎重に検討する」ことです。かわいさだけで判断するのではなく、その犬種の性格、必要なケア、費用などをしっかりと理解し、自分の生活と照らし合わせたうえで判断することが大切です。
次に、保護犬や譲渡犬を選ぶことも有効な手段です。販売ではなく、譲渡という選択肢が広がれば、命を商品として扱うことへの依存も少しずつ減っていきます。また、ブリーダーから迎える場合でも、繁殖の方針や飼育環境を確認し、信頼できる相手かどうか見極めることが求められます。
加えて、「生体販売をしているペットショップで購入しない」という意思表示も重要です。このような選択をする人が増えれば、販売方法自体の見直しや、生体販売の縮小につながる可能性があります。
最後に、動物愛護に関する情報を発信することも、社会の意識を変える一歩になります。SNSやブログで学んだことや体験をシェアするだけでも、多くの人が考えるきっかけになります。
このように、売れ残りという問題に対して「何もできない」と感じる必要はありません。私たちが日々選択する行動が、未来の犬たちの運命を左右する力を持っているのです。
ペキニーズの売れ残りに関するよくある質問
ペキニーズの売れ残りに関して、よく寄せられる質問をまとめました。購入を迷っている方や保護犬を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ペキニーズが売れ残りになる理由を総括
記事のポイントをまとめます。
- ペキニーズはマイペースで猫のような性格を持つ
- 独立心が強く従順なタイプではない
- 初心者にはしつけが難しいと感じることがある
- 他の犬や人に対して距離を置く傾向がある
- 信頼した相手には忠実で深い愛情を示す
- 被毛の手入れが毎日必要なレベルで大変
- 顔のシワのケアや皮膚の健康管理も必須
- 呼吸器系に弱く暑さに特に注意が必要
- フローリングなどで滑りやすく関節に負担がかかる
- 価格が高く、相場は20万円〜40万円前後
- 出産頭数が少なくブリーディングが難しい
- 血統や見た目によって価格が大きく変動する
- 購入をためらう人が多く売れ残りにつながる
- ペットショップでは一定期間を過ぎると売れにくくなる
- 売れ残った個体は価格を下げられるか店舗移動となる
- 引取り業者に渡されると劣悪な環境の可能性がある
- 激安で売られる背景には健康や飼育環境の問題が潜むこともある
- 個人販売では価格は安いが健康保証などがない場合がある
- 信頼できる販売者かどうかの見極めが重要
- 里親制度や保護犬譲渡で出会える可能性もある
- 里親は無料でも医療費などの負担がある場合がある
- 保護犬は譲渡条件や審査があるため誰でも迎えられるわけではない
- 保護団体は信頼できるが、引取り屋は注意が必要
- 飼ってからの性格やケア面でのギャップで後悔する人もいる
- 性格や特徴を事前に理解すれば後悔は減らせる
- 売れ残りを減らすには私たちの選択と意識が鍵となる