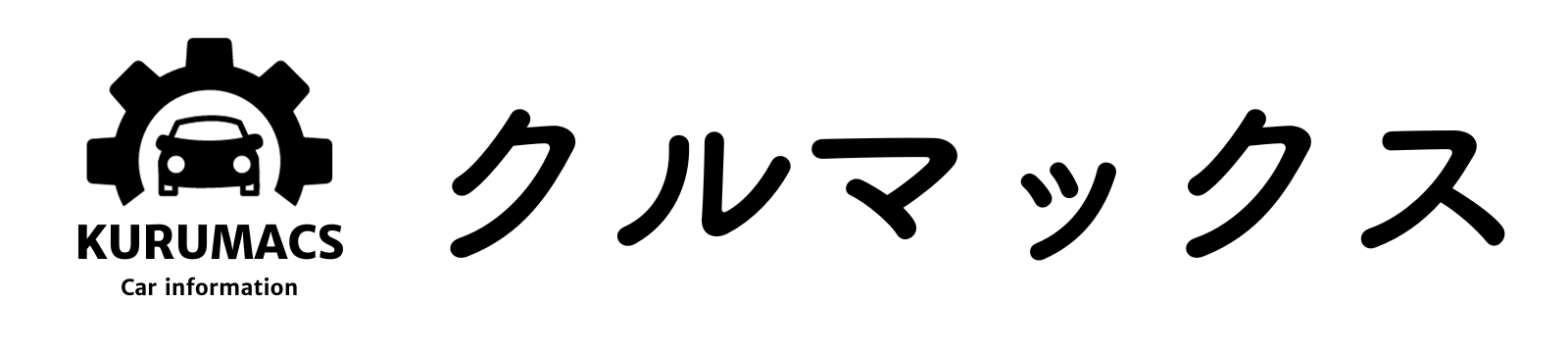マツダCX-60に対して「失敗作では?」と感じる人が増えています。
理由は、発売直後から相次ぐリコールや不具合、そして乗り心地の悪さや電子制御の不安定さなど、実用面での問題が多く報告されているからです。
さらに、株主総会でマツダ自身が「開発や造り込みが不十分だった」と認めたことも信頼性を揺るがす要因となりました。
SNSでは「がっかり」「やばい」といったリアルな声が拡散され、購入を検討していた人の不安をあおっています。
この記事では、CX-60の不具合の実態から今後の改善点まで、失敗とされる理由を整理し、検討中の方に向けた冷静な判断材料を提供します。
- CX-60が「失敗」と言われる主な理由と背景
- 発売後に発生した不具合やリコールの実態
- SNSやユーザーからのリアルな評価や声
- 今後の改善点や購入時に確認すべきポイント
CX-60失敗と言われる理由と不具合の実態

- CX-60が不具合だらけとされる背景
- 株主総会で明かされたCX-60失敗の原因
- CX-60にがっかりという声が広がったきっかけ
- 乗り心地が悪いというユーザー評価
- Twitterで広がるCX-60の不具合報告
- CX-60の不具合一覧とリコール履歴を整理
- やばい・売れないと評される根拠とは
- 試作不足とコスト問題が招いたCX-60失敗の構造
- 初期モデルに多いトラブルとその傾向
CX-60が不具合だらけとされる背景
結論から言うと、マツダCX-60が「不具合だらけ」とされる背景には、システム面での不安定さと開発段階での課題が大きく関係しています。
その理由は、CX-60がマツダの新たなFRラージモデルとして初めて導入された車種であり、最新の電動化システムや複雑な制御プログラムを搭載していたからです。新しい技術を詰め込んだ反面、設計や検証が十分でなかった部分があったと考えられています。
具体的には、納車から短期間で複数のリコールが発生し、リコール対象にはトランスミッション、電動パワーステアリング、マイルドハイブリッド用バッテリーなど重要な部品が含まれていました。また、プログラム更新によって新たな不具合が生まれるケースもあり、ユーザーからの不満が広がる要因となっています。
さらに、SNSやレビューサイトでも「走行中に勝手にブレーキがかかる」「ハンドルがまっすぐに保てない」「リアゲートが閉まらない」など、日常使用に支障が出るトラブルが多数報告されています。Twitter上では「#CX60不具合」といったタグが拡散され、注目を集めました。
このように、機械的な問題に加えてソフト面での信頼性にも不安があったことから、「不具合だらけ」という印象が強まったといえるでしょう。
株主総会で明かされたCX-60失敗の原因
CX-60の「失敗」が一気に現実味を帯びたのは、2023年に行われたマツダの株主総会での発言がきっかけです。マツダ自らが「開発や造り込みが不十分だった」と認めたことが、事態の深刻さを裏付けました。
その背景には、短期間で相次いだリコールやサービスキャンペーンの多さがあります。具体的には、発売からわずか数カ月の間に4件以上のリコールが出され、しかもそれが制御系や動力伝達装置といった車の安全性に直結する部分だったため、信頼性が大きく損なわれました。
また、改善対応として配布された修正プログラムの中には、別の新たな不具合を生む“爆弾入りアップデート”とも言えるものも存在し、ユーザーやディーラー側からの不満も強まりました。これらの対応の遅さや情報開示の不透明さも「失敗」と評価される一因です。
株主総会では、CX-60の品質問題が企業全体のブランド価値を損なうリスクとして厳しく追及され、経営陣は「再発防止と信頼回復に取り組む」と表明しました。しかし、この発言自体が「失敗」を認める公式な姿勢と受け取られ、結果として世間の不信感を強める形にもなっています。
このように、CX-60の不具合は単なる個別の問題ではなく、企業の姿勢や開発体制そのものにまで疑問符が付いたことで、「CX-60=失敗車種」というレッテルが貼られるに至ったのです。
CX-60にがっかりという声が広がったきっかけ

結論から言えば、CX-60に対して「がっかり」と感じる声が広がった理由は、ユーザーの期待値と実際の使用感に大きなギャップがあったからです。
この車はマツダが満を持して投入した新世代モデルで、「プレミアムSUV」「走りの進化」「上質な内装」など、発表当初から非常に高い評価を受けていました。特にFRプラットフォームや高級感あるデザインに魅力を感じて購入を決めた人も多く、新型に対する期待は非常に高かったのです。
しかし、実際に乗り始めたオーナーからは「ソフトウェアのバグが多い」「リコールが多すぎる」「ハンドル操作が不安定」などの報告が相次ぎました。また、バック時に急ブレーキがかかるなど、日常運転に支障が出るトラブルもありました。
SNS上では「買わなければよかった」「高い買い物なのに残念」といった声が拡散され、一部では「これはテスト車両では?」という皮肉まで飛び交いました。
つまり、宣伝と現実の差が大きかったことが、多くのユーザーにとって“がっかり体験”となり、その声が一気に広まったのです。
乗り心地が悪いというユーザー評価
結論として、CX-60は「乗り心地が悪い」と感じるユーザーが少なくありません。その理由は、マツダ独自の足回りのセッティングと車両重量のバランスにあります。
元々、マツダ車は「走りの良さ」を重視しており、CX-60もその例に漏れません。硬めの足回りやシャープなハンドリングは、ドライバーの操作にしっかり反応する一方で、路面の凹凸や段差を拾いやすく、同乗者には「ゴツゴツ感」「突き上げ感」が伝わりやすくなっています。
特にリアサスペンションの設定については不満の声が多く、「段差を越えるたびに音がする」「後席が跳ねるような感じがある」といった口コミも見られました。これにより、長距離ドライブでは疲れを感じるという意見もあります。
ただし、この硬さを「スポーティ」と捉える人もいるため、評価は分かれる部分です。ですが、快適性を重視して選んだ人にとっては、期待と異なるフィーリングに戸惑い、「乗り心地が悪い」という印象を持ってしまうのです。
Twitterで広がるCX-60の不具合報告
結論から言えば、CX-60の不具合に関する情報はTwitterで急速に広まり、多くのユーザーの不安や不満が可視化されました。
その背景には、購入者や試乗者が体験した不具合をリアルタイムで発信しやすいSNSの性質があります。Twitterでは、「ハンドルが勝手に動く」「バック時に急ブレーキがかかって危険」「Apple CarPlayが頻繁にブラックアウトする」といった具体的な症状が多数報告されています。
また、こうした投稿に対して共感やリツイートが集まり、似たような体験をしたユーザー同士がつながることで、不具合の存在がより多くの人に広まっていきました。
特に注目されたのは、「ディーラーで何度も修理したのに直らない」「対策パーツがあるのに既存のオーナーには無償で提供されない」といった対応面での不満です。このような発言が多くの共感を呼び、CX-60に対するネガティブな印象を強める一因となっています。
つまり、Twitter上の声は、単なるクレームではなく「実際に起きている問題を可視化した集合体」として、車選びにおいて無視できない情報源となっているのです。
CX-60の不具合一覧とリコール履歴を整理
結論として、CX-60は発売から現在までに多くの不具合が報告され、それに伴って複数回のリコールやサービスキャンペーンが実施されてきました。
不具合の主な内容は、制御プログラムの不調によるエンジンの再始動失敗、電動パワーステアリングの異常、バックドアの開閉トラブル、車両の警告灯の誤作動など、多岐にわたります。国土交通省へのリコール届け出だけでも、2023年4月・11月、2024年2月など数回に分けて行われており、それぞれに対象パーツの交換やプログラム修正が行われています。
特に注目すべきは、ソフトウェアのアップデートが繰り返されるたびに新たな問題が発生し、「リプロ(再プログラム)」のたびに混乱が広がっている点です。また、すでに販売済みの車両には対策パーツが装着されないこともあり、オーナー間では不公平感が指摘されています。
このように、リコールや修正が行われている一方で、「根本的な解決には至っていない」という印象を持つユーザーが多く、安心して乗れる状況とは言いがたいというのが現状です。購入を検討している方は、これらの履歴を確認し、リスクを理解したうえで判断することが大切です。
やばい・売れないと評される根拠とは

結論から言えば、「やばい」「売れない」と評されているのは、CX-60に対する実際のトラブルとユーザー評価の積み重ねによるものです。
その理由として最も大きいのは、不具合の多さです。購入直後からリコールが繰り返され、「バック中に急ブレーキがかかる」「ハンドルが勝手に動く」「モニターが真っ暗になる」といったトラブルが頻繁に報告されています。特にSNS上では、購入者の生の声が広まりやすく、不安を抱く人が急増しました。
加えて、マツダ側の初動対応が後手に回った印象もあります。不具合があってもすぐには認められず、「様子を見てください」との対応が多かったため、信頼感が損なわれました。
もう一つの要因として、販売面での失速があります。CX-60は話題性のある新型車として注目されていましたが、思ったほど売れていません。実際、発売からしばらく経っても街で見かける機会が少なく、販売店からも「期待したほど動いていない」との声が出ているのが現状です。
このように、「やばい」「売れない」という評価は単なる噂ではなく、実際の不具合と消費者の不安が重なって生まれたものだと言えます。
試作不足とコスト問題が招いたCX-60失敗の構造
結論として、CX-60が「失敗」と評される原因の根底には、試作不足とコスト削減の影響があります。
まず、CX-60はマツダが新たに開発したFRプラットフォームを採用しており、開発コストは非常に高かったと言われています。そのため、できるだけ開発費を抑える方針がとられ、試作段階での走行テストや検証の機会が少なかったとされています。これは、実車が市場に出てから不具合が次々と判明したことにもつながっています。
また、車両設計に関しても「見切り発車だった」との指摘があります。細かい不具合や使い勝手の悪さが目立ち、結果として「完成度の低いまま発売された」という印象をユーザーに与えてしまいました。
さらに、プログラム制御が中心となる設計が進められた一方で、それを支えるシステムの安定性や互換性に問題があったことも明らかになっています。つまり、設計思想としては先進的でも、それを実現する技術力や検証体制が追いついていなかったのです。
こうした背景が重なり、初期型オーナーは「開発のテストドライバーのようなもの」と揶揄される状況になってしまいました。試作不足とコスト削減が、CX-60の信頼性に大きな影を落としたと言えるでしょう。
初期モデルに多いトラブルとその傾向
結論から言えば、マツダCX-60の初期モデルには、電子制御系を中心に多くのトラブルが集中しています。これは新技術や新プラットフォームを採用した際に、十分な検証が不十分だったことが原因と考えられます。
まず目立つのは、プログラム関連の不具合です。たとえば、ハンドルが勝手にカクカク動く、誤作動による急ブレーキがかかる、車載モニターが突然ブラックアウトするなど、走行に支障が出るトラブルが発生しています。これらはソフトウェアのアップデートで対応されているものの、再発するケースも少なくありません。
また、乗り心地や足回りに関する不満も多く報告されています。段差を越えるときに車体が跳ねる、異音がするといった症状があり、リアショックアブソーバーやスタビライザーの交換対応が行われた例もあります。
さらに、ドアやバックドアの開閉不良といった使い勝手に関するトラブルも目立ちます。センターコンソールのフタがバネの不具合でうまく開閉できない、リアゲートがきちんと閉まらないといったケースもあります。
このように、初期モデルには機械的な故障よりも、電子系・制御系のトラブルが集中している傾向があります。そして、それらが重なった結果として「CX-60は不具合だらけ」といった印象につながっているのです。
新型車の初期モデルには一定のリスクがあるものですが、今回のCX-60ではその数と内容の多さが問題視されています。特に、安全性に関わる部分での誤作動は、ユーザーにとって大きなストレスとなり、評価にも強く影響しています。
CX-60失敗を乗り越えるための改善と購入判断

- 不具合解消に向けたマツダの対応策
- リコール対応から見るCX-60の今後
- 改良モデルに期待される改善ポイント
- 初期型購入のリスクとユーザーの心構え
- 一般ユーザーと専門家で分かれる評価
- 他社SUVとの比較で見えるCX-60の課題
- CX-60購入を検討する前にチェックしたい点
- CX-60は失敗作なのかを総括
不具合解消に向けたマツダの対応策
結論として、マツダはCX-60に対して段階的に不具合解消を進めていますが、すべての問題が解決されたわけではありません。メーカーとして対応の姿勢を見せている一方で、ユーザーの信頼を取り戻すには時間がかかる状況です。
その理由として、まずソフトウェアの更新、いわゆる「リプロ」と呼ばれるプログラム修正が頻繁に行われている点が挙げられます。たとえば、ドライバー認識機能や自動ブレーキの誤作動などに関しては、複数回にわたりソフト更新が実施されています。
さらに、ハードウェア面での対応も見られます。リアショックアブソーバーやハンドル関連部品の交換、バックドアのロック機構の修正など、実際に部品を取り換える対応が進められています。これは不具合の再発防止につながる重要な措置です。
ただし、こうした対応がすべての車両に自動で行われているわけではありません。不具合が出て初めて対処されることが多く、ユーザー自身が症状を認識し、ディーラーに相談する必要があります。この点は注意が必要です。
今後の改善に期待しつつも、現在のCX-60オーナーには、不具合が見られた際はすぐにディーラーに相談する行動が求められます。マツダの対応策は一歩ずつ進んでいますが、完璧な状態には至っていないのが現状です。
リコール対応から見るCX-60の今後
結論から言えば、これまでのリコール対応の内容を見ると、CX-60はまだ「発展途上」のモデルと言えます。新技術の採用にともない、不具合が続いているため、今後の改善が強く求められています。
リコールはすでに数回行われており、たとえばトランスミッション制御プログラムの修正や、電動パワステ部品の交換、バッテリー制御の問題など、多岐にわたる不具合が対象となっています。国土交通省への届出件数も増加傾向にあり、内容を見る限り、車の基本的な走行や安全性に関わる部分での問題が多いです。
このことから、現時点でCX-60を「完成された車」と見るのは難しい状況です。しかし一方で、リコールを通じて問題を明確にし、対応を進めていることは、メーカーとしての改善姿勢の表れとも取れます。
今後のマイナーチェンジや年次改良で、こうした課題がどれだけ解消されるかが、CX-60の評価を大きく左右するポイントになるでしょう。また、次に購入を検討する人にとっては、「今後どこまで改良されるか」を見極めることが重要です。
このように、リコールの対応状況を見れば、マツダの本気度や車の完成度を判断する一つの材料になります。将来的な安定性を望むのであれば、現時点では慎重な判断が必要かもしれません。
改良モデルに期待される改善ポイント

結論から言うと、今後のCX-60の改良モデルでは「電子制御の安定性」と「乗り心地の改善」が大きな期待ポイントです。初期型で課題とされた部分を中心に、実用性と安心感の向上が求められています。
理由としては、これまで多くの不具合が電子制御系で発生してきたからです。たとえば、ドライバーアシスト機能の誤作動や、パーソナライゼーション機能の不認識など、プログラム関連の問題が目立ちました。今後はソフトウェアの熟成によって、安定した制御が期待されます。
また、足回りの硬さや不快な振動についても多くの声が寄せられています。マイルドハイブリッドやラージFRプラットフォームの新しさは魅力ですが、それに伴って乗り心地に課題があるのも事実です。次の改良モデルでは、ショックアブソーバーやサスペンションの見直しが進められる可能性があります。
さらに、Apple CarPlayの安定性、センターコンソールの作り込みといった細かな部分にも改善の余地があります。ユーザーの声を活かし、細部まで使いやすさを高めることが、ブランドの信頼回復につながるでしょう。
このように、次のモデルではソフト・ハードの両面での見直しが進めば、より満足度の高い一台に進化する可能性があります。
初期型購入のリスクとユーザーの心構え
初期型モデルを購入する場合、結論として「トラブルをある程度受け入れる心構え」が必要です。すべてが完成されているとは限らないため、慎重さと柔軟な対応力が求められます。
その理由は、どのメーカーでも新型車の初期型は、実際の走行環境での使用によって初めて見えてくる不具合があるからです。CX-60の場合も、発売直後から数多くのリコールや改善策が発表されており、まさに“開発段階に近い状態”で販売された印象があります。
具体的には、ドライバー補助機能の誤作動、異音やパーツの故障、操作系の不具合など、幅広いトラブルが報告されました。このような状況では、ディーラーとの継続的なやり取りや、アップデート対応をこまめに受ける姿勢が不可欠です。
さらに、改良部品が新車にしか適用されないケースや、ユーザーが不具合を指摘しないと対応が行われない場合もあるため、一定の“気付き”と“対応力”が必要となります。
このように考えると、初期型購入者は単なる消費者というより「実地テストに協力している立場」として、広い心で付き合っていく姿勢が求められます。とはいえ、こうした経験を通じて、車が改善されていくという楽しみもあります。
購入前にはリスクを理解し、事前に十分な情報を集めた上で、自分に合った選択をすることが大切です。
一般ユーザーと専門家で分かれる評価
結論から言えば、CX-60の評価は「一般ユーザー」と「専門家」で大きく異なります。見ているポイントや重視する価値が違うため、感想や満足度に差が出るのは自然なことです。
まず、一般ユーザーが重視するのは「使いやすさ」「快適性」「安心感」といった日常に直結する要素です。そのため、「乗り心地が硬い」「機能がうまく動かない」「不具合が多い」といった点に敏感に反応します。特にSNSなどでは、リアルな声が共有されやすいため、不満やストレスの声が目立ちやすくなっています。
一方で、専門家や車評論家の評価では「新しいプラットフォームの挑戦」「FRベースによる走行性能の進化」など、構造面や設計思想に注目が集まります。トルク感や重量バランスといったマニアックな視点から評価されることも多く、技術的には面白い車という見方も少なくありません。
このように、日常の使いやすさを重視するか、新技術への評価を重視するかで、CX-60への見方は変わってきます。どちらの意見も参考になりますが、購入を考える際には、自分がどの立場に近いかを見極めて情報を取ることが大切です。
他社SUVとの比較で見えるCX-60の課題

結論として、CX-60は「新しい挑戦が多いぶん、完成度の面では他社SUVに見劣りする部分がある」と言えます。外観やスペックでは魅力的に見える一方で、細かな部分の使い勝手や品質で差が出ています。
たとえば、トヨタのハリアーやホンダのCR-Vといった競合車は、モデルとして成熟しており、機能の安定性や快適性が高く評価されています。これに対してCX-60は、新しい技術を多く取り入れているため、ソフトウェアの不具合や初期トラブルが目立つ傾向があります。
また、ドイツ車のメルセデスやBMWなどと比べても、走行時の電子制御やインテリアの細部の作り込みなどで、細かな差が感じられることがあります。特に、ステアリングの挙動やサスペンションの調整については「詰めが甘い」と感じるユーザーも少なくありません。
もちろん価格帯の違いもあり、一概に優劣を決めることはできません。しかし、同価格帯のSUVと比較した場合、「機能は多いが仕上がりにムラがある」という印象を持たれるケースが多いようです。
このような比較を通じて見えるのは、「挑戦的な設計が裏目に出てしまった部分がある」ということです。今後の改良によって、こうした課題がどこまで解消されるかが注目されます。
CX-60購入を検討する前にチェックしたい点
結論からお伝えすると、CX-60の購入を考える際には「最新モデルかどうか」「不具合への対応状況」「試乗による実感」の3点をしっかり確認することが重要です。
まず注目したいのは、購入予定の車が初期型か改良後のモデルかという点です。CX-60は発売当初に多くの不具合が報告されており、その後リコールやプログラム修正が行われてきました。販売時期によっては、これらの対策が反映されていない可能性があるため、製造年月やアップデートの有無をディーラーでしっかり確認しましょう。
次に、不具合やトラブルへのメーカーとディーラーの対応状況も重要です。SNSやレビューサイトを見ると、対応に差があるケースも見受けられます。購入前に、近隣のディーラーが信頼できるかどうか、サービス体制が整っているかをチェックするのも安心材料になります。
さらに、必ず試乗を行うことをおすすめします。特にCX-60は「乗り心地が硬い」「ハンドルが不安定」などの声も多く、カタログスペックだけでは分かりにくい部分があります。高速道路や段差の多い道など、普段よく使う環境に近い状況で運転してみると、より現実的な判断がしやすくなります。
このように、CX-60は魅力的なポイントがある一方で、注意点も少なくありません。購入後に「失敗だった」と感じないためにも、これらのチェック項目は事前にしっかり押さえておくべきです。
CX-60は失敗作なのかを総括
記事のポイントをまとめます。
- CX-60は新型FRプラットフォーム採用で設計検証が不十分だった
- システム面の不具合が多く「不具合だらけ」との印象が広がった
- 納車直後から複数のリコールが発生している
- 制御プログラムのアップデートで新たな不具合が発生したケースもある
- SNSではリアルな不満の声が拡散されている
- Twitterでは「#CX60不具合」の投稿が目立っている
- 「開発や造り込みが不十分」と株主総会でマツダ自身が発言した
- 安全系のトラブルが多くユーザーの信頼感を損ねている
- 高い期待値に対し実使用での不満が多く「がっかり」評価が増えた
- バック時の誤作動ブレーキやハンドル不安定など日常使用に影響が出ている
- 乗り心地が硬く突き上げ感が強いとの声が多い
- 電子制御やソフトウェア関連の不具合が特に多い傾向にある
- 改善策としてリプロやパーツ交換は実施されているが再発も多い
- 不具合への初動対応が遅くメーカーへの不信感が広がった
- 「売れない」「やばい」との評価はトラブルや対応への不満が原因
- 試作不足やコスト削減の影響で開発精度が下がったとされている
- 初期型購入者は「開発テストドライバー」と揶揄されている
- 他社SUVと比べて完成度や安定性で劣る印象がある
- ユーザー評価と専門家評価に大きなギャップがある
- 購入前には製造年月や対応履歴の確認が必要とされている